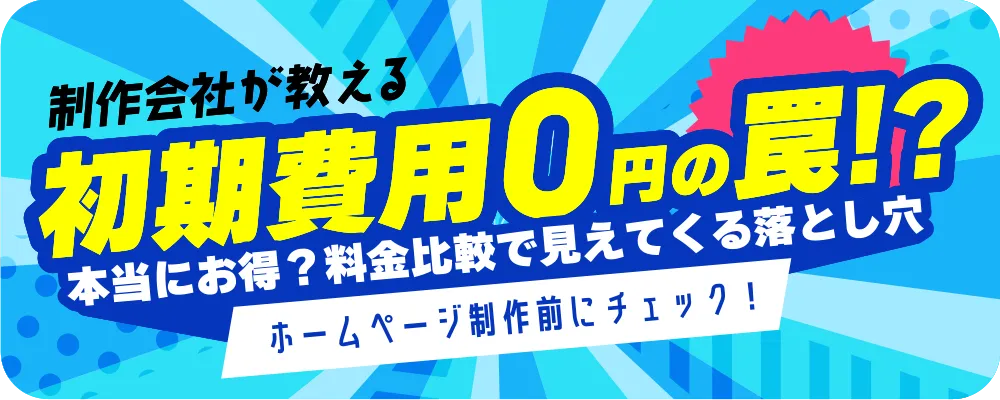Journal
石板から紙の本へ。紙とデジタルのメリット・デメリットとWEB制作-PART2
デジタル媒体の書籍やコンテンツは、例えるならば未だ紙の本への発展途中にいる石板のようなものかもしれません。
紙の完全デジタル化は起きるのか?紙とデジタルのメリット・デメリットとWEB制作の記事では「デジタル書籍の致命的なデメリットは、紙に比べて脳の処理能力が低くなる点?」というデジタル書籍のデメリットについて触れました。
- バックライトの影響
- テキストの視認性
- 深い処理の欠如
このような紙との違いが、集中力や記憶力の処理への影響を与える可能性があり、教育現場でデジタル教科書を採用すると紙の書籍に比べて記憶の定着が難しいと言われていたりします。
特に電子書籍では、紙と違ってパラパラページをめくって自然とページ間で行き来しながらテキストを「再確認」することが容易ではないという点が「3.深い処理の欠如」につながり、記憶の定着に影響しています。
先のページをチラッと見たり、前のページをチラッと見たり、数ページ前後をパラパラ高速でページをめくりながら一瞬だけチラッと目に入れる。
こういった紙の書籍を読むときに行っている何気ない動作が、記憶の定着のためには重要なのです。
しかし例えばWEBサイトのようなデジタルデバイスでは、今見ているページのみが画面に表示され、それ以外のページを見るためには「よし、別のページを見るぞ」と脳が意識してページ遷移動作をする必要があります。
原始的な石板に掘られた文字を読むように、別のページを読むために意を決して「よいしょ」と次の石板を持ってくるようなものです。
そんな石板から紙の本へと近づくために、デジタルコンテンツはまさに日々進歩を遂げている途上と言えます。
デジタルコンテンツでも紙の書籍に近い操作性や直感的なナビゲーションを実現するため、さまざまな人間工学的工夫が施されている例を見ていきましょう。
1. スマートフォンのWEBページ表示における慣性スクロール
一番身近な例はスマートフォンの慣性スクロールです。
指を離した後もしばらくスクロールが続く仕組みで、紙の書籍を素早くめくる動作に近い感覚をデジタルで再現しています。
- 高速な情報探索が可能
例えば、長い記事やSNSのフィードを流し読みしながら、目に入った重要な箇所でスクロールを止めて詳細を読む、といった直感的な操作が可能。 - 流れるような読書体験
物理的な本で「ページをパラパラとめくる」動作に似た感覚を提供し、デジタル特有の違和感を軽減。 - 人間工学的な操作性
指を動かす強さや速度に応じてスクロールのスピードが変わるため、読者の意図に応じた操作が可能。
2. AdobeのPDFビューアにおけるページサムネイル機能
Adobe AcrobatなどのPDFビューアには、ページのサムネイル(縮小版)を一覧表示する機能があります。
これにより、デジタル書籍や文書でも物理的な書籍のように、全体の構造を把握しながら自由に行き来することができます。
- ページ間の移動が容易
目次やサーチ機能だけでなく、視覚的にページのレイアウトを確認しながら、必要な箇所にすぐジャンプできる。 - 紙の書籍の「めくり戻し」に近い体験
書籍の途中で気になった箇所を見返す際、サムネイルを頼りに素早くアクセスできる。 - 視覚的な記憶を活用
ユーザーが「この図のページを探したい」と思ったときに、サムネイルで瞬時に見つけられる。
3. Apple BooksやKindleのページめくりアニメーション
デジタル書籍でも、紙の本をめくるようなアニメーションを取り入れることで、直感的な読書体験を提供しています。
- 視覚的なつながりを維持
ページが一瞬見えることで、めくった感覚を再現し、記憶の定着を助ける。 - スワイプ操作と組み合わせることで直感的な操作が可能
4. スクロール型電子書籍の登場(Webtoonや縦読み漫画)
最近の電子書籍ではWEB漫画などを中心に、従来のページめくり方式ではなく、韓国発のWebtoonのような縦スクロール型のフォーマットが増えています。
賛否両論ありますが、スマートフォンでの読みやすさを追求した結果生まれた形態です。
- スクロールで読み進めるため、紙の本よりもスムーズな読書体験を提供
コミックのコマ割りの特性に特化した、そもそもページの区切り自体がない連続性を実現。 - 目の負担が少なく、直感的な操作でページを遷移できる
5. E-inkディスプレイ(電子ペーパー)
ページ遷移の工夫以外にも、KindleやKoboなどの電子書籍リーダーに搭載されているE-ink(電子インク)ディスプレイは、紙のような視認性を持ち、画面のちらつきを抑え、長時間の読書でも目の疲れを軽減します。
- バックライトではなくフロントライトを使用
光源がディスプレイの前面または周囲に配置されていて、目に優しく、長時間の読書でも集中力を維持しやすい。 - 紙に近い見た目
コントラストが高く、文字がくっきり。
太陽の下でも反射しにくいので、屋外でも視認性が高い。
このように、慣性スクロールやサムネイル表示のように紙の本には存在せずデジタルならではの機能でありながら、紙の本に近い直感的ページ遷移を実現したケースや、E-inkディスプレイ、ページめくりアニメーションなど紙の本の要素をデジタルコンテンツにも取り入れたケースなど様々な工夫で、デジタルコンテンツもただの石板から進歩していっています。
今後も、視線追跡や触覚フィードバックなど、新たな技術が取り入れられることで、さらに直感的で記憶に残りやすいデジタル読書が実現する可能性があります。
ホームページをはじめとするWEBコンテンツの制作現場でも、積極的にこういった工夫を取り入れることでユーザビリティのさらなる向上が図れるのではないでしょうか。
一瞬で目的のページに遷移したり、特定のキーワードを検索したり、気になった内容について他のコンテンツを同時に見ながら理解を深めたり、そういった点でデジタル媒体は紙媒体よりも優れています。
石板からもっともっと進歩できれば、デジタルコンテンツは最終的に紙媒体のコンテンツを超える集中力や記憶力をもたらす優れた学習ツールになる可能性を秘めていると言えるでしょう。