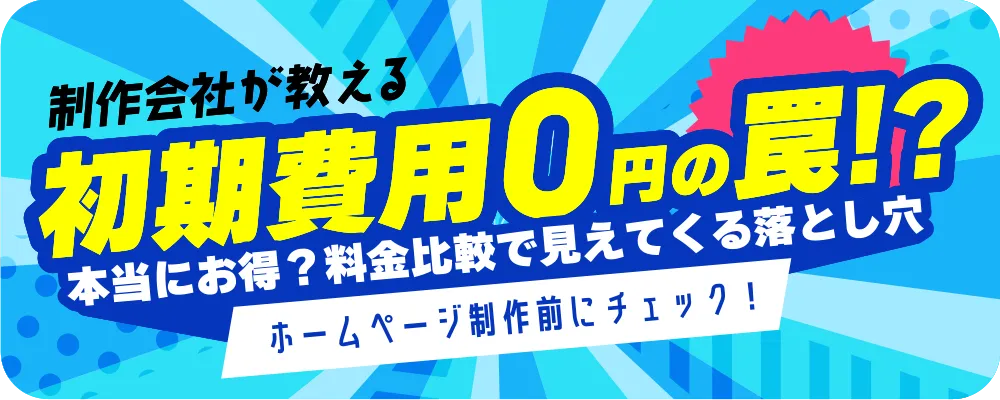ChatGPTに「Study Mode(学習モード)」が登場!
OpenAIは2025年7月29日(現地時間)に、ChatGPTに新機能「Study Mode(学習モード)」を導入しました。
これは、ただ答えを与えるのではなく、ソクラテス式の対話(逆質問形式)やヒント、自己省察のプロンプトを用いて、学習者が自ら理解を深めるよう誘導する学習体験を提供する機能です。
現在、ChatGPTの Free、Plus、Pro、Team の各プランで利用可能で、数週間以内に ChatGPT Edu(教育機関向けプラン) にも展開される予定のようです。
英語圏から順次導入されるようなので、この記事を書いている現時点で、ジャンプスのスタッフの日本語のChatGPTにはまだ切り替えモードの選択肢が出現していません。
導入されると、通常のチャットと学習モードを自由に切り替えできるようになるようです。
学習モードの特徴をチェック!
- インタラクティブプロンプト
ユーザーの現在のレベルや目標を確認するために質問を重ね、ユーザーが主体的に考えるようサポート。直接答えを求めても「一緒に考えましょう」と返し、学びを促します。 - スキャフォールディング
情報を段階的に提示し、理解しやすい構造に整理。概念の複雑さに応じて徐々にレベルを上げることで、認知的負荷を軽減します。 - パーソナライズ
過去のチャット履歴(Memory機能がオンの場合)に基づいて、ユーザーに合ったアプローチを提供。理解チェックやフィードバックもユーザーごとに調整されます。 - 理解度チェック
クイズやオープンエンドの問題を出題し、進捗や理解度に応じてフォローアップや解説を行います。
Web制作会社での活用は?
コーディング・プログラミング学習に使える可能性あり
この学習モードは主に大学生に向けた新機能のようですが、ジャンプスのようにWEB制作を行っている会社でもスタッフの学習に使えそうです。
これまではJavaScriptやPHPなどの学習では、専門の講座を受講するのが一般的でしたが、この学習モードを使えばChatGPTで専門知識の学習もできる可能性があります。
Web制作会社やデザイン会社の初心者研修、LMS(学習管理システム)補助、スキル向上支援などで以下のように活用できます。
- ロジック構築やアルゴリズム思考の補助
JavaScriptの非同期処理やCSSレイアウト、DOM操作の理解を深めるステップバイステップの対話学習に有効。 - 疑似コード・設計レビュー
「まず何をやるべきか?」という疑問に対して「設計図を描いてみよう」など逆質問し、思考整理を促します。 - 記憶定着と応用演習
簡単なクイズや実装の確認課題を通じて、応用力と理解力を測りながら繰り返し学習が可能。 - チーム研修や新人教育
一斉説明ではなく、個々の進度や理解度に合わせて柔軟に対応できる個別指導スタイルにも利用できます。
例)HTML/CSSレイアウトの学び方
例えば通常のモードでは、Flexboxでセンタリングしたい場合、コードを書いてくれるようにプロンプトを入力すれば、ChatGPTはコピペすればいい完成形のコードだけを返してきます。
これは即実務で使えるのですが、意味も分からずコピペだけしていてもスタッフ自身のスキル向上にはなりません。
学習モードではどうなるかというと……
-
1.Study Modeをオン
チャットの上部にある切り替え用の選択肢からStudy Modeを選ぶと学習モードになるようです。
-
2.「Flexboxでセンタリングしたいんですが」と入力
→ChatGPTが「どの要素を中央に配置したいですか? 親要素の構造は?」などと逆質問。
-
3.ユーザーが答える
→「では、そのHTML構造をもとにまずFlexコンテナを設定してみましょう」→CSSコード案を提示し、イントロ→応用→確認という流れで理解を深める。
このように、直接コードを返してくるのではなく、完成形のコードに行きつくようにスタッフをサポートしてくれるようです。
メリット
- ユーザー自身の考えを促す対話型学習で、受動ではなく能動的な習得が可能。
- 誤りやつまずきをその場でフィードバックし、記憶の定着を助ける。
- 単なるコード生成ではなく、仕組みの理解もサポート。
ただし、例によってAIはシレっと間違った内容を返してくることもあるようなので、教材や指導者による補足も必要とのこと。
ここは実務で使用していても間違ったコードを渡されることがあるのと同じようです。
学習モードの今後の展開予定
今後は、目標設定・進捗トラッキング・視覚的サポートなどの機能強化が予定されており、より学習支援ツールとして充実していく見込みのようです。
教育機関向けの導入事例やAPI連携・LMS統合についても、今後の発表が期待されます。
教育現場だけでなく、ビジネス現場や研修にも応用できる可能性を秘めたこの新しい「Study Mode」、ぜひ制作現場のスキルアップや学習のツールとして活用していきたいですね!