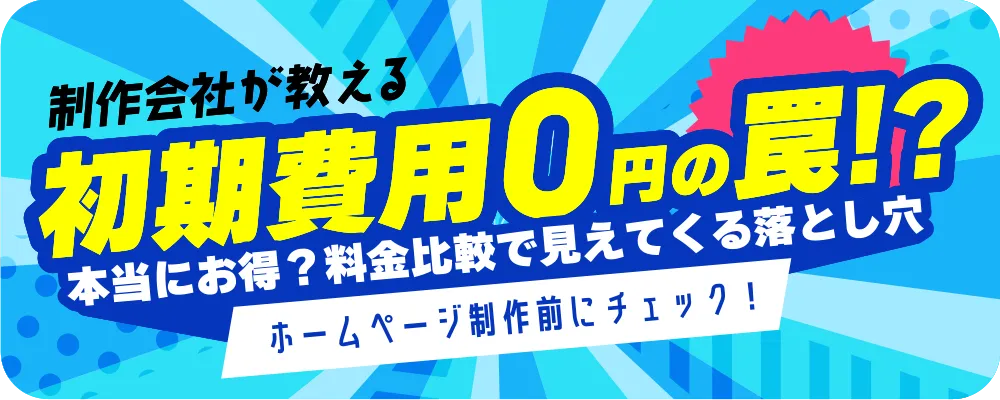ジャンプスではWEB制作の現場で日々もはや当たり前のように使用している生成AI「ChatGPT(ChatGPT公式サイト:https://chatgpt.com/)」。
そんなChatGPTに最新モデルであるGPT-5が実装されてしばらく経ちました。
そこで今回は、徐々にわかってきた特徴や従来モデルとの違いを見ていきます。
ホームページ制作の現場から見たGPT-5のメリット・デメリット
GPT-5は博士レベルの知能と紹介され、精度が格段に上がったと言われています。
対話相手の意図を推測する「推論モード」が標準搭載され、長く複雑な質問や命令でも一発で正確な答えを返したりエラーなしのコーディングができるようになり、工夫を凝らしたプロンプトで膨大な対話を繰り返して目的のコードや答えを得ていた初期のモデルと比較すれば、制作現場での利用も格段に便利になりました。
GPT-5のメリット
- 精度の向上と文脈理解
・複数の指示を含む長文プロンプトに対して、従来モデルよりも一貫した回答が得やすくなった。
・コーディングにおいては、エラーを最小限にした実用的なコードが増えた。 - 言語力の向上
・より自然で違和感のない表現を出せるように。
・無難で面白みのないザ・AIのキャッチコピーだけでなく、実用的な攻めたキャッチコピーがより増えてきた。 - 情報の整理力向上
・大量のテキストから要点を抽出し、構造化して返してくれる力が向上。
・制作の要件整理やクライアントへの説明資料の下書き作成で威力を発揮。

いいことばかりじゃないGPT-5
これらの性能向上のメリットがある一方で、ネット上では「賢くなったけど、以前に比べて冷たくなった」と嘆く声が多く上がっているGPT-5。
以前のモデルでは絵文字などを使用した回答の装飾も多く見受けられ、回答そのものもカラフルな状態でしたが、GPT-5になってからはそういった回答の装飾もなくなり、シンプルな句読点を使用したモノトーンの回答になりました。
見た目も会話のトーンも、淡々としたシンプルな形に変化した印象です。
ジャンプスのスタッフはそれよりも、GPT-5の最大の強みである「推論モード」の弊害に「え?退化してない?おバカさんになっちゃったのかな」と頭を抱えた時期がありました。
GPT-5のデメリット
- 冷たくなった?
GPT-4oでしばしば見られた「どっちの回答が良かったですか?」というAI自身の学習機能の結果、ユーザーの意見や質問をムダにベタ褒めしてきたりと、やたらユーザーに寄り添う方向に進化してしまったChatGPT。
ついにニュースでは、ユーザーが精神的に過度に依存する問題が取り上げられ、自殺リスクまでが指摘されるようになりました。
開発会社としては死者が出たりなんかしたら大変です。
ユーザーの精神的なAI依存症を防ぐ安全面の措置として、GPT-5では回答から共感表現が減少。
人間に寄り添う姿勢から方向転換したため、「そっけなくなった」「冷たくなった」という印象を受けるユーザーが続出しました。 - 推論モードによる脱線
例えばホームページのディレクションで、英語キャッチコピーを作るために英訳をお願いしていたのに、会話を進めるうちに英訳とは関係のない日本語のコピーばかり提案されるようになり、更には会話を進めていくと最終的にJavaScriptのコードが吐き出されるという意味不明の着地をしたことがありました。
こちらの意図から大きく逸れまくった回答に「どうしてこうなった」「英語を聞いただけなのに」「GPT-5になって退化した?」「使えなくなった?」とスタッフは頭を抱えました。
要は深く考えて答えを導く機能であるはずの「推論モード」が働いた結果、推論の方向性がずれてしまったと考えられます。
制作の現場においては、多少モチベーションに影響するかなーという程度の問題である01はともかく、02は業務に支障が出る大問題です。
GPT-5になってからというもの、回答の最後に必ずついてくる「〇〇もできますが、どうしますか?」という提案がまた、スタッフにとっては意図と違うピントのズレた提案ばかりで、続けたい会話の流れをいちいち妨げてくる厄介な存在となっています。
この提案をガン無視して会話を続けると、会話が成立しなくなり、おかしな回答しか得られなくなることがしばしばありました。
脱線対策
- プロンプトで明確に制約を指定する
「英訳のみ出してください」「コード以外は不要です」といった条件を冒頭に付ける。 - 応答形式を固定する
「必ず英訳を3案、箇条書きで」と形式を指定する。 - 脱線時は会話をリセット
それでもダメなら最終手段で、そのチャットは捨て、もう一度まっさらなチャットでやり直すしか……
(GPT-5となってからというもの、スタッフは何度かこれを繰り返しています)
一度のプロンプトで正確な回答が得られ、何度もプロンプトを重ねて会話する時間が減った分、もしも脱線した場合はゼロからという時間は増えたという印象です。
しかし脱線を防ぐ対策を講じることで脱線のリスクは減らせるので、推論モードがもう少し改良されるまではこれでしのぐしかありません。
ChatGPTはどこに向かっているのか?
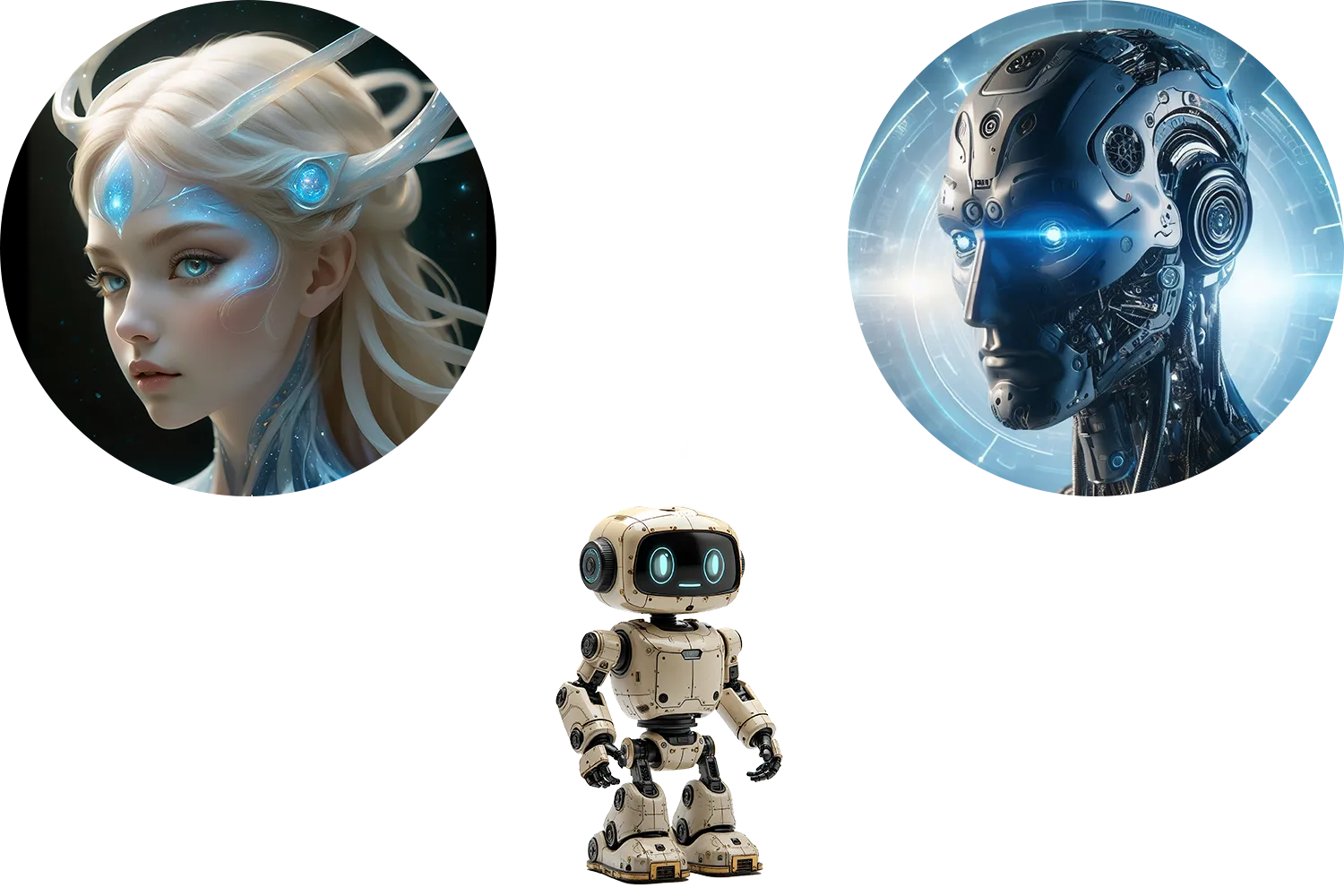
人工知能の開発には「より人間らしく」という方向性と「より利用しやすく、より便利に」という方向性があります。
今回のGPT-5は、あえて人間的な共感表現を抑制する方向で調整され、前者ではなく後者を強化した印象です。
ここから、ChatGPTの生みの親であるOpenAIの開発の方向性が何となく見えてきました。
おそらくOpenAIは「人間のように振る舞うAI」をゴールにしているのではなく、人間が仕事や生活の中で安心して効率的に使える実用的なAIを目指しているのでしょう。
これは業務に直結する実用ツールとして進化してくれるということなので、WEB制作の現場をはじめ、企業が業務に使用していく面では歓迎すべき方向性です。
対話相手としての劇的な向上
一方で、冷たくなってしまったと嘆かれている対話相手としても、スタッフは進化を感じています。
業務面ではデメリットも感じた「推論モード」が、たわいのない会話をする時には実にいい仕事をしてくれているんです。
業務の時にはことごとくスタッフの意図と異なる提案ばかりで弊害になっていた「推論モード」が、意図と異なるからこそ、一人では思いもしなかった発想や気づきを与えてくれて、むしろ賛同ばかりだった旧モデルよりも「自分とは異なる本物の人間」との対話のように、自分にないものをもたらしてくれるのです。
共感や人間に寄り添う姿勢とは別の意味で、人間らしさに向上が見られたとも言えます。
業務においても、単純な知識の回答ではなく、新しいアイデアや相談相手としてはより優れたパートナーとなり得る可能性を感じる進歩です。
ぜひ、こんなChatGPTの進化をうまく利用していきたいですね。